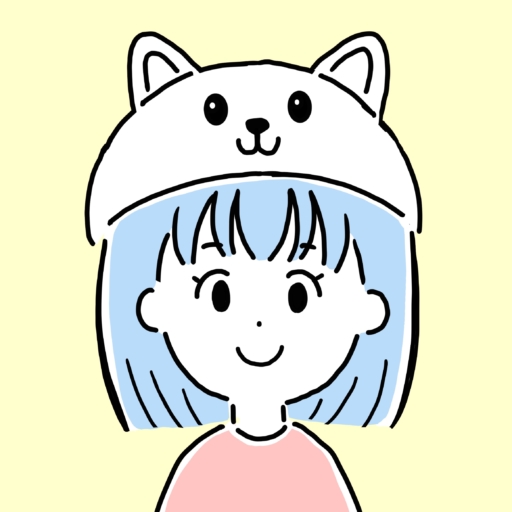
今回は、「アドラー心理学」を子供との関わりに取り入れたことで、子供に大きな変化があったよ!といった話をしようと思います。
長男は幼稚園の年少時、手を出すことでトラブル続きでした。
悩んだ私が藁を掴む思いで学んだのが「アドラー心理学」。
それは、その後の私の育児の「軸」となりました。
手を出す子だった


息子は当時(0歳8ヶ月~3歳)お友達に手を出す子でした。
とてもエネルギッシュで、叩く、噛む、引っ張るは日常茶飯事。。
まだ力の加減も知りませんでした。
そんなこんなで、相手の子の保護者とトラブルが耐えなかったのです。
アドラー心理学に出会った
私がどのように「子供の手を出す」問題を自分の中で処理し、解決し、そして気持ちよく前進できたかといいますと。。
アドラー心理学を用いた『STEP勇気づけセミナー』の参加がきっかけです。
ここでは私がセミナーを通して学んだ結果、このように問題をクリアできたという一つの実体験をそのまま書こうと思います!
『STEP勇気づけセミナー』とは?
『STEP勇気づけセミナー』は、心理学のアドラー学派の専門家たちによって考え抜かれたものです。
何千人もの親の協力を得て有効だと確認した、子供のしつけについての哲学のようなもので、グループワークによる学習方法を取り入れています。
息子の「手を出す問題」に本格的に悩んでいた時、ママ友の1人が私に声をかけてくれたのがこの『STEP勇気づけセミナー』でした。
数あるセミナーの中で私が最終的にこの『STEP勇気づけセミナー』を選んだ理由は、グループワークに惹かれたからです。
目から鱗の内容
実際に受けたセミナーは、なんとも心がスッキリする内容!
「これは誰の問題か」をまず考え、見極める。
その基本精神は簡単明瞭で、目から鱗でした!
演習で聴いた、
『子供の「良い行動」のすべてが親の功績ではないように、好ましくない言動を、すべて親の責任とすることなどできることではありません』
という言葉に、どんなに勇気づけられたかわかりません。
この考え方を基にして、子供も、母親である私も、お互いの人格を尊重することが大切だと思いました。
子供に対して
子供の人格を尊重すること。問題は「手を出す」こと。
「私たち親子の課題=怒りをコントロールして争いを避ける」
と、方向性がはっきり見えました。
驚いたのは「反映的な聴き方」をした後の子供の変化!
反映的な聴き方をすることによって、自分の存在を認めてもらっていると感じるかならのではないかと思います。
以前はいつもキョロキョロ他人を気にし、話しても目を合わせてくれなかったわが子です。
そして、自分が確実にできるものしかやろうとしない、自信の無さが見られました。
しかし「反映的な聴き方」をすると、私の目を見て自分を信じ、新しいことに挑戦しようと言う意欲が見られたのです。
子供はそのように満たされている時、他人を気にしません。
その反応はとても早く起こり、「こんなに変わるものなのか!」と驚きました。
自分自身に対して
自分自身を大切にすることを学びました。
私に必要なことがこのように(以下)クリアになりました。
- 「子供に起こる事全てのことは自分の責任」という考えをやめること。
- 「課題の分離」をして、必要以上に罪の意識を背負わない事。
- 謝るべきことは謝る、だけど自分の権利も大切にする。
幼稚園のママへの対応
まず相手の話を聞くこと。困っているのは相手だから、反映的な聴き方で。暴力については謝る。
そして私の答えですが、
「ただそれが私の関わりの責任とされるのは疑問だし、そう言われると悲しい。
私から子供にも伝えるけど、ママからも思ったことを直接子供に伝えて欲しい。その方が本人に伝わる。
子供の行動すべては見れないし、本人はまだ小さいけど責任ある行動をとってもらいたいと思っている」
という旨を冷静に、iメッセージで伝えます。
気持ちの変化
「自分が正しい、相手は間違っている」と思うことがすでに争いの始まりで、これは「価値観を押し付ける」ことになりますよね。
私も気づかぬうちにしています。。
ですので、幼稚園のママも私も皆一緒。ですね。
そう思うと彼女を恨むのではなく、彼女のおかげで内省でき、多くの気づきがあったと前向きに捉えられます。
新しい園での様子
幼稚園でのトラブルが原因で休園、その後退園といった苦渋の決断をした私ですが、その後すぐに夫の転勤により引越しが決まりました。
子供は転園することになったのです。
私は、新しい園でも息子はまた「手を出すんじゃないか」と不安があり、ある日恐る恐る、新しい担任の先生に園での息子の様子を聞いたところ、
「クラスの中心にいます。自己主張がちゃんとでき、悲しいことがあって泣いても、すぐに楽しいことを見つけて向かっていきます。そんな〇〇君がみんな大好きです。」
と、まさかのお褒めの言葉をいただいたのです!
前の園では親子共々疎まれ、悩んでいた時のことを思い出すと涙が。。
このように転園した頃(4才)には一方的な暴力を振るうことは無くなっていました。
けど、ケンカは全く無かったかと言えばそうではなく。
なかなか元気な子が多いクラスだったようで、息子はしょっちゅう傷を作って帰ってきました。
また、息子は売られたケンカは買っていた様子を先生から聞きました(汗)
先生は本当に危なくない程度に見守って下さっていたようです。
年長の卒園間近になれば、そのようなことも無くなっていました。
今では
あの手を出す息子も今では小学生になりました。沢山のお友達ができ、みんなと仲良く過ごしています。
また、基本的に人が好きの様です。
暴力は今ではありません。ことあるごとに手を出していた昔が、嘘のよう。
周りのママ友に「〇〇君が手を出す子だったなんて信じられない!」と言われるくらい、息子は落ち着き払っています。
ぜひ長い目で
子供の「手を出す行為」は、今思えば一貫性のものだったように思います。
「何でもっと長い目で見てあげられなかったんだろう?」と思わずにはいられません。。(←実はこれに尽きるとも言える)
子供の課題を、大人はもっと長い目で見守ってあげたいものですね!
最後に
私から悩めるお母さんに勇気づけとして、、
今あるお子さんの問題はいつまでも続きません。常に物事は変化します。
サポートが必要な場合もあると思いますが、ぜひご自身に合った良い人、良い場所を見つけられるよう願っています!
【アドラー心理学があれば大丈夫】手を出す我が子はこうして変わった、いかがでしたか?
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!
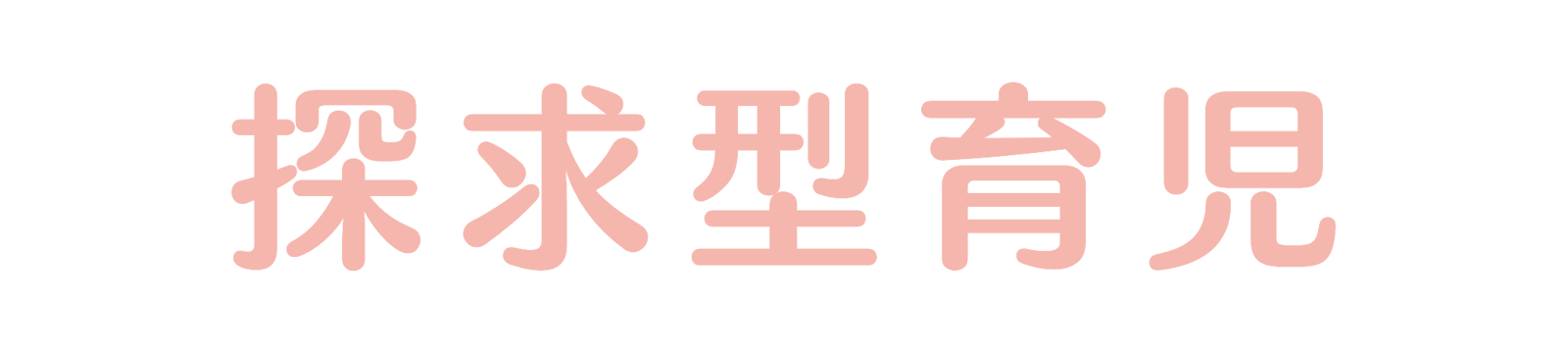
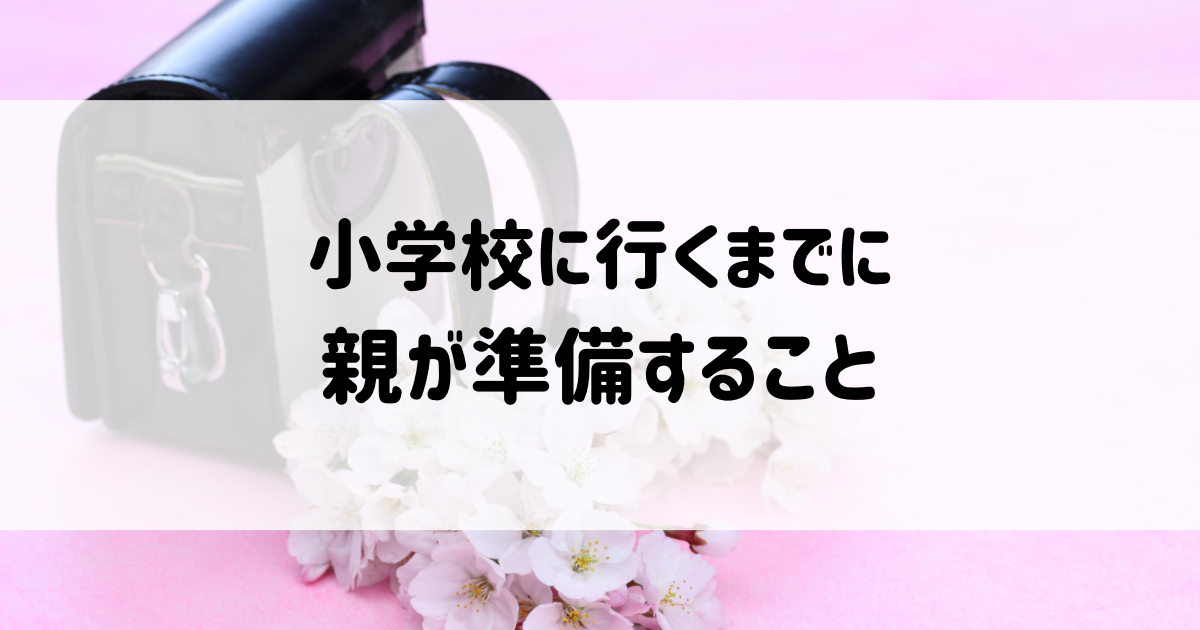







コメント
コメント一覧 (1件)
前回のブログにコメントしましたが、新しい園では自分から手を出したりはなかったんですね!とても安心しました。アドラー心理学、理解するには少し難しかったです(^^; 反映的な聴き方って、具体的にはどんな感じなんでしょうか。